
マキサカルシトール製法事件(最高裁第二小法廷判決)
- 業務分野
最高裁第二小法廷は、本判決で、平成10年ボールスプライン事件最高裁判決の判示した均等の5要件のうちの第5要件に関して、出願時に容易に想到される均等物・方法が、出願時の特許請求の範囲に記載されていない場合に、均等を主張できない特段の事情に当たるか否かについて、以下のように明確な判断を示し、この問題の論争に終止符を打った。
「(1) ・・・・・・・出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったともいい難い。また、上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで、特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のように時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることが出来ることとなり、相当とはいえない。
そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」
「(2)もっとも、上記(1)の場合であっても、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また、以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない、出願人と第三者の利害を適切に調製するものであって、相当なものというべきである。
したがって、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、それを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなど特段の事情が存するというべきである。」
(当事務所のコメント)
本判決は、均等の第5要件に関する論争を解決したが、特許法における均等論の本質に立脚して判示がなされている。特に、特許出願人が、特許出願時に将来の侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載することは困難であり、一方、第三者は、時間をかけて特許を検討することができるのであるから、出願時に容易に想到される均等物・方法が特許請求の範囲の記載に含まれなかったというだけのことで、均等の主張が許されなくなる特段の事情が存するとはいえないと判示しているのは、完璧な特許出願を行うのは困難であるという現実を踏まえて、特許権者と第三者の利益の調和を、均等論の適用においても図ろうとするものといえる。
そもそも、出願時に容易に想到できる均等物・方法というのは、出願時の技術水準において、明細書に記載された特許発明から均等物・方法が容易に想到できるという意味であって、出願時に、発明者や出願人が、均等物・方法を容易に念頭において出願手続を行うことを意味しない。実際には、出願人は、広いクレームを取得することは考えるとしても、特定の態様の均等物・方法を出願時にあれこれ考えて、クレームを作成しているわけではない。
最高裁判決によって均等論が明確に認められたことの意味は、特許出願人が、出願手続で、必ずしも、広いクレームを追い求める必要がないということである。均等論が認められず、文言侵害のみである場合には、出願人はできるだけ広いクレームを追い求めざるを得ない。しかし、広いクレームは、拒絶・無効理由を含む可能性が高く、これを避けるために補正・訂正で限定すれば、将来の均等の主張の余地がなくなる。これに対して、均等論が認められる要件が確立すれば、必ずしも広いクレームではなく、出願時から、発明の特徴の明確な、補正の必要のない独立クレームで出願することにより、無効になりにくく、事案によっては均等論による保護も期待できる権利を取得するという特許出願実務が可能となる。均等論が発明の保護に資する最も大きな理由は、広いクレームを追い求めることなく、発明の保護を図れる点にあるといえる。
(マキサカルシトール製法事件の事案内容)
マキサカルシトール製法事件では、東京地裁も知財高裁(特別部)も、均等侵害を認定した。実質的な争点は第5要件だけであったといえる。すなわち、マキサカルシトール製法事件は、典型的な均等の事案であるといえる。マキサカルシトール製法事件の事案内容については、こちら。
この業務分野を取り扱う弁護士
-
 平川純子Junko Hirakawaパートナー
平川純子Junko Hirakawaパートナー -
 尾崎英男Hideo Ozakiパートナー
尾崎英男Hideo Ozakiパートナー -
 小林雅人Masato Kobayashiパートナー
小林雅人Masato Kobayashiパートナー -
磯部健介Kensuke Isobeパートナー
-
 井口加奈子Kanako Inokuchiパートナー
井口加奈子Kanako Inokuchiパートナー -
鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
-
 近藤祐史Yuji Kondoパートナー
近藤祐史Yuji Kondoパートナー -
 上野潤一Junichi Uenoパートナー
上野潤一Junichi Uenoパートナー -
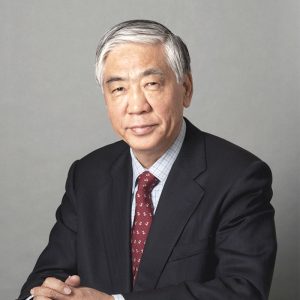 佐藤恒雄Tsuneo Satoオブ・カウンセル
佐藤恒雄Tsuneo Satoオブ・カウンセル -
 鈴木隆史Takashi Suzukiオブ・カウンセル
鈴木隆史Takashi Suzukiオブ・カウンセル -
 棚橋祐治Yuji Tanahashiオブ・カウンセル
棚橋祐治Yuji Tanahashiオブ・カウンセル -
江黒早耶香Sayaka Eguroカウンセル
-
 バヒスバラン薫Kaoru Vaheisvaranカウンセル
バヒスバラン薫Kaoru Vaheisvaranカウンセル -
家村洋太Yota Iemuraアソシエイト
当事務所が手掛けた「特許訴訟・仲裁」の判例
- ペン型注射器事件
- オリンパス職務発明事件
- 椅子式マッサージ機事件
- 電話の通話制御システム事件
- 味の素 v 中外製薬―遺伝子組換え形質転換CHO細胞の浮遊培養事件
- マンホール構造用止水可とう継手事件(判例時報2014号127頁)
- 無効審決取消請求事件(タキソールを産生する細胞の培養方法)
- 携帯電話番号識別子事件
- 抗CD20抗体発明の権利帰属事件
- 洗浄組成物事件
- エアコン熱交換器フィン職務発明事件
- マキサカルシトール製法事件(知財高裁大合議判決)
- マキサカルシトール損害賠償事件(東京地裁民事47部判決)
- マキサカルシトール製法事件の事案内容
その他「特許訴訟・仲裁」の判例
- 特許権の存続期間の延長登録
- プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁大合議判決
- 「切り餅」事件控訴審終局判決
- 「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件控訴審判決
- 実施可能要件とサポート要件
- 洗浄組成物事件
- 専用実施権を設定した特許権者による差止め請求の可否
- 「写ルんです」特許権侵害事件
- インクカートリッジ事件最高裁判決
- 職務発明訴訟における当事者の主張の整理
- 他社との共同発明における職務発明の相当の対価の額の算定(テレフォンカード事件)
- 発明者の認定
- 精製組成物の発明の新規性
- 発明の技術的範囲の解釈
- ケーブル用コネクタ事件
- 粗面仕上金属箔事件
- 開き戸の地震時ロック方法事件
- 中空ゴルフクラブヘッド事件
- 電話番号情報の自動作成装置事件
- ドリップバッグ事件
- 特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立要件
- 「ナイフの加工装置」事件
- 特許権の存続期間の延長
- ライセンス契約と独占禁止法
- マンホール構造用止水可とう継手事件
- 「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害
- 特許を受ける権利と共同訴訟参加
